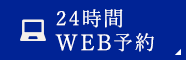交通事故の診療
 交通事故に遭った直後は神経が興奮しているため痛みを感じにくく、2~3日経過してから痛みが現れるということもあります。放置していると症状が悪化する可能性があるため、早期検査・早期治療が大切です。
交通事故に遭った直後は神経が興奮しているため痛みを感じにくく、2~3日経過してから痛みが現れるということもあります。放置していると症状が悪化する可能性があるため、早期検査・早期治療が大切です。
当院では、交通事故が原因の様々な症状に対する治療を行っており、診察やレントゲン検査などを行って状態を確認し、適切な治療を実施しております。
症状の有無を問わず、交通事故に遭った方は早めに当院までご相談ください。
このような症状はありませんか?
以下のような症状が起きている場合、放置すると症状が悪化してしまう恐れがありますので、お早めに当院までご相談ください。
- 手足の痺れ
- 頭痛
- 背部痛
- 腰痛
- 膝痛
- 動かしにくさ・こわばり
- むち打ち症の可能性がある症状(痛み、耳鳴り、吐き気、めまいなど)
- 上記以外の部位の違和感や痺れ、痛み など
交通事故後の治療までの流れ
1保険会社に連絡
まずは保険会社に連絡を入れ、交通事故の治療のために当院を受診することを伝えます。保険会社から当院に治療依頼の連絡が入ることで、患者様は費用の負担なく治療を受けられます。
2スタッフによる事故や症状の内容確認
当院のスタッフが事故の状況や症状の有無・内容などについて詳しくお伺いします。
3医師の診察
 まずは診察を行い、必要なレントゲン検査を実施していきます。
まずは診察を行い、必要なレントゲン検査を実施していきます。
4レントゲン検査
 レントゲン検査で骨折などの骨の異常がないかを確認します。
レントゲン検査で骨折などの骨の異常がないかを確認します。
5治療方針の決定
診察・画像検査の結果を説明し、今後の治療方針についてご相談します。
6リハビリの開始
 症状の悪化を防ぐため、早期からリハビリを開始します。理学療法士の管理のもと、患者様の状態に応じた治療を行います。当院では最新の医療機器を用いた物理療法を併用することもあります。
症状の悪化を防ぐため、早期からリハビリを開始します。理学療法士の管理のもと、患者様の状態に応じた治療を行います。当院では最新の医療機器を用いた物理療法を併用することもあります。
交通事故の治療費
自賠責保険について
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走行する車やオートバイは加入が義務付けられています。交通事故被害者を守ることを目的とした保険です。加害者の経済状況に関係なく、被害者は最低限の救済を受けられるようになっており、加害者の自賠責保険に対して請求を行えます。
当院では、健康保険または自費診療による治療を行っています。健康保険は、健康保険組合に第三者の行為による傷病届を出すことで適用され、被害者に変わり健康保険組合が加害者に医療費を請求します。
治療費について
加害者・被害者の双方が損害保険の使用に同意した場合、費用負担なく治療を受けられます。
交通事故についてよくある質問
交通事故の治療に伴う通院に必要な手続きはありますか?
当院を受診する前に保険会社に連絡を入れて頂きます。当院が保険会社から連絡を受けている場合は、患者様は費用を負担することなく治療を受けられます。なお、保険会社に連絡する前に受診された場合、治療費はお支払い頂く必要がありますが、その後、当院に保険会社から連絡が入れば、お支払い頂いた治療費は返金いたします。
交通事故による治療で他院を受診していましたが、転院できますか?
現在受診している医療機関で紹介状を発行してもらい、それを持参してください。また、転院前に保険会社にも今後当院を受診する旨を連絡して頂けると、転院をスムーズに進められます。
事故から数日後に痛みが現れたのですが、治療を受けられますか?
治療できますので、早めに当院までご相談ください。交通事故では時間が経つにつれて症状が現れるということもあります。交通事故に遭った場合は、ちょっとした違和感や痛み、無症状の場合でもお早めに受診してください。
診断書や証明書を発行してもらえますか?
当院では交通事故に遭った際の診断書や証明書の発行にも対応しています。ご相談ください(文書料の自己負担が必要な場合があります)。
治療はいつまで続けられますか?また、補償費や慰謝料はどうすれば受け取れますか?
治療については、保険会社から打ち切りの通告があるまでは患者様の自己負担なく続けられます。また、後遺症が残った場合、補償や慰謝料を請求するには交通事故による後遺症を証明する後遺障害診断書が必要となります。当院でも後遺障害診断書の作成・発行に対応しています(文書料の自己負担が必要です)。
仕事中・通勤中に発生した災害による怪我(労災)
労災保険は、通勤中や業務中に発生した災害が原因となり、労働者が怪我を負う、疾患を患うなどが発生した場合、あるいは障害が残る、死亡するなどが生じた場合に、労働者本人や遺族を保護するための保険です。当院では労災保険法に沿った治療を行っています。
業務中の災害
 労働基準法では、業務中に発生した災害が原因となり、その業務に従事していた労働者が怪我を負う、疾患を患う、障害が残る、死亡した場合、使用者は各種補償を行うことが義務付けられています。ここでいう「労働者」は正社員に限らず、派遣社員やパート、アルバイトなども当てはまります。
労働基準法では、業務中に発生した災害が原因となり、その業務に従事していた労働者が怪我を負う、疾患を患う、障害が残る、死亡した場合、使用者は各種補償を行うことが義務付けられています。ここでいう「労働者」は正社員に限らず、派遣社員やパート、アルバイトなども当てはまります。
なお、業務中に発生した災害が労働者側の不注意によるもので、会社側に過失がない場合も対象となります。
通勤中の災害
通勤中に発生した災害が原因となり、その業務に従事していた労働者が怪我を負う、疾患を患う、障害が残る、死亡した場合も労災保険の対象となります。ここでいう「通勤」は、自宅と職場の往復や職場間の移動で、通勤や業務との関係がない行為や通勤経路から外れている場合は適用外となります。なお、日常生活上必要な行為であり、最小限で行っていると判断された場合は適用対象となります。具体的には、通勤中の日用品購入、業務に関わるスキルアップのための通学、投票などの選挙行為、医療機関への通院などが挙げられます。
労災についてよくある質問
労災での初診時に必要な物はありますか?
初診時は会社から受け取った書類をお持ちください。一般企業にお勤めの方で通勤中に発生した災害の場合は16号の3の用紙を、業務中に発生した災害の場合は5号用紙が必要となります。また、公務員の方は別の用紙が必要となります。
なお、緊急で書類の用意がなく受診された場合は、一時的に治療費をお支払い頂きますが、後日、書類をご持参いただければご返金します。
治療費は一切かからないのですか?
労災での受診は患者様の治療費負担は一切ありません。なお、労災と認定されるまでの間は健康保険で治療費を支払って頂きますが、認定後は支払って頂いた分は返金いたします。
災害が労働者側の不注意によるものであっても業務と災害の因果関係があると認められれば労災保険の対象となります。この認定は労働基準監督署が担当します。
後遺障害診断書は発行してもらえますか?
労災で障害補償給付を受け取るには、労働基準監督署に申請書を提出して手続きを行う必要があります。この申請書の裏面は医療機関が作成した後遺障害診断書となっており、この診断書をもとに後遺障害の有無やその内容を確認します。当院でも後遺障害診断書の作成・発行が可能です(文書料の自己負担が必要な場合があります)。