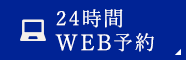当院のリハビリテーションについて
 当院では理学療法士の管理のもと、運動療法と徒手療法を中心としたリハビリテーションを行っています。
当院では理学療法士の管理のもと、運動療法と徒手療法を中心としたリハビリテーションを行っています。
運動療法は、ストレッチや専用の機器を用いて、筋力アップや機能の回復を目指します。一方で、徒手療法は治療者が患者様の身体に触れ、患部の可動域を拡大し、筋肉のこわばりの緩和を目指すマッサージのようなものです。
定期的に状態を確認し、患者様と相談しながら最適な治療となるよう改善しています。
症状が改善するまで時間がかかると「大丈夫だろうか?」と心配になることもあると思いますが、スタッフがしっかりサポートしますので、ご安心ください。
リハビリテーションの対象となる症状
リハビリテーションの対象となる症状や疾患は多岐にわたります。肩こりや痺れ、動かしにくさ、骨折や捻挫などがあり、それ以外にもスポーツの怪我の予防や運動機能の向上などが挙げられます。患者様のお悩みやご希望に応じてリハビリを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
- 痺れや麻痺、こわばりが起きている
- 関節に痛みや変形が起きている、動かしにくい
- 首や肩のこり・腰痛などの慢性症状により、日常生活に影響が出ている
- 階段・坂道だけでなく、平地を歩くのにも支障が出ている
- 歩き始めると痛みが出るので、休みながらしか歩けない
- 日常動作(食事・トイレ・着替えなど)がうまくできない
- 術後も痺れや痛み、動かしにくさなどの症状が続いている
- スポーツによる障害で痛みや動かしにくさなどの症状が続いている
- 交通事故が原因のむち打ち症(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)が治らない
首や肩のこりなどの症状は加齢や体質と思って放置される方が多いですが、適切な診断・治療・リハビリテーションにより症状の解消が期待できます。また、関節リウマチや骨粗鬆症などの疾患も、治療とともに運動療法などのリハビリテーションを行うことで、運動機能が回復する可能性があります。
筋肉はいくつになっても鍛えることが可能で、筋力が向上することで骨や関節への負担を抑えることができます。また、身体の安定性や代謝・血行が良くなることで、全身の健康・生活の質を高める効果も期待できます。
状態・時期に応じたリハビリテーション
同様の怪我や疾患であっても、全身の状態、症状の内容や重症度、回復段階などによって、リハビリテーションの内容は異なります。
急性期
受傷・疾患の発症から3週間頃までの急性期では、薬物療法で患部の状態や痛みを改善します。必要に応じて装具を用いて患部を固定し、痛みを軽減させます。また、筋力や可動域の低下、関節の拘縮を防ぐために運動療法などを併用することもあります。
回復期
炎症や痛みなどが治まる回復期では、根本的な原因を解消するために運動療法を併用したリハビリテーションを行い、再発予防を図ります。運動療法は、筋力や柔軟性を高め、物理療法によって運動療法の効果をサポートします。また、身体に負担がかからないような姿勢・動作についても丁寧に指導しております。
当院の運動療法、徒手療法、物理療法
運動療法
動作がスムーズにできない、力を入れづらい、動くと身体が痛む、転倒しやすく歩くのが不安など、動作やバランス、姿勢に関係する症状をトレーニングで改善します。
筋力増強訓練
(筋力トレーニング)
患部周囲の筋肉を鍛え、患部にかかる負荷を和らげます。なお、無理をすると症状が悪化する恐れがあるので、患者様の状態や症状に応じた適切なトレーニングをご提案しています。
歩行訓練
歩行訓練では、杖や松葉杖、歩行器、平行棒を使用した訓練、階段の昇降や出っ張りがある場所を歩く訓練などを実施します。
関節可動域訓練
関節可動域訓練は、関節の可動域が狭くなっており動作に痛みを伴う方に行うトレーニングで、関節の可動域を拡げることが目的となります。痛みを少し感じる位置まで関節を動かす動作を繰り返し行いますが、動作を止めると痛みはほとんど残りませんので、ご安心ください。
バランス能力の訓練
バランスが良い状態では転びにくく、動作時に特定の部分に負担が集中することはありません。バランス能力は静的バランスと動的バランスの2種類に分けられ、いずれかの能力が低下していると転倒リスクが高まります。
静的バランスは、静止した状態で外から力が加わっても動かずに平衡を保てる能力で、動的バランスは動作状態で外からある力が加わっても平衡を保つ能力です。
バランス能力には様々な要因が関わっているため、改善するためには正しく原因を特定し、多元的なアプローチが必要です。まずは、バランスを崩しやすくなる状況、方向、頻度など様々な視点から原因を考えていきます。
高齢の方には、杖や歩行器などの介助支持物も含めて検討し、長期的なサポートを行います。
徒手療法
徒手療法は、理学療法士が手を使って行う治療で、痺れや痛みなどの症状、運動機能の改善のために行います。
関節モビライゼーション
関節の可動域が狭くなり動かしにくさを感じている患者様に対して行う治療です。ゆっくりと様々な方向に関節を繰り返し動かすことで、少しずつ可動域が拡がります。
軟部組織モビライゼーション
筋や腱、靭帯など軟部組織が原因となる症状を軽減し、可動域の制限を回復させるために行うマッサージです。可動域の制限が重度の場合は関節モビライゼーションも併用することがあります。
物理療法
超音波や水力、熱など物理的な刺激を加えることで、血液、リンパ液の循環や代謝を改善し、痛みなどの症状の軽減が期待できます。運動療法と併用することでより効果を得やすくなります。
温熱治療
患部を温めることで血行を促し、筋肉の緊張をほぐします。なお、怪我や炎症がある場合は事前に医師に相談の上、実施するようにしましょう。
超音波治療
人間には聞こえない高い周波数(20kHz以上)の音波を患部に照射し、身体の深部で温熱マッサージを行います。生体内に存在する微小な気泡が拡張と圧迫を繰り返すことで、細胞が刺激されて活性化し、血流が改善して痛みが軽減することで、筋肉の緊張もほぐれます。