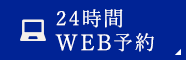骨粗鬆症とは
 骨粗鬆症は、骨に含まれるカルシウムなどが減少することで、骨強度(骨密度・骨質)が低下し、骨折しやすくなる状態です。
骨粗鬆症は、骨に含まれるカルシウムなどが減少することで、骨強度(骨密度・骨質)が低下し、骨折しやすくなる状態です。
加齢に伴って骨密度は減少しますが、特に女性の場合は女性ホルモンの減少に伴って骨密度が急激に減少する傾向があります。そのため、骨粗鬆症の発症者の約80%は女性となっており、更年期や閉経後に好発します。
骨粗鬆症は骨が脆くなった状態のため、軽い衝撃でも骨折しやすくなります。重症化した場合、自重により背骨が潰れるように骨折し、寝たきりの状態になってしまう恐れがあります。また、自覚なく骨折する(「いつの間にか骨折」)こともあり、「背中が丸くなった」「身長が縮んだ」などで初めて骨折していたことに気付くということも多いです。
身長低下などの骨格の変形により生活の質(QOL)を低下させ、自立した生活の障害となります。背中や膝が曲がって身長が徐々に低下しますが、その大きな原因は脊椎の圧迫骨折です。身長が4cm以上低下すると生活の質が明らかに低下することがわかっています。背中が曲がり、身長が低下することにより重心が5cm以上前方へ移動すると、転倒リスクが約2.5倍増加することが報告されています。
写真は、骨を走査型電子顕微鏡で観察したものです。
左は正常の海綿骨で、ギッシリと骨がつまっていて、しっかりと体を支えています。右は骨粗鬆症で、骨はスカスカになり、体の重みを支えきれません。
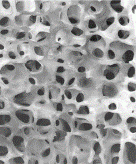 正常の海綿骨
正常の海綿骨 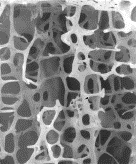 骨粗鬆症の海綿骨
骨粗鬆症の海綿骨骨粗鬆症の原因
女性は閉経後に女性ホルモンが減少しますが、女性ホルモンは骨密度・骨質を維持する働きがあり、女性ホルモンが減少することで骨粗鬆症を発症しやすくなります。
栄養バランスの偏った食事、過剰なダイエット、アルコールの過剰摂取、喫煙、運動不足などがリスク要因となるため、若い方でも生活習慣が乱れていると、骨粗鬆症を発症する可能性があります。
また、糖尿病や慢性腎不全、関節リウマチなどの疾患が原因となって骨粗鬆症を発症することもあります。その他にも疾患の治療薬としてステロイド剤を長期間服用し続けていると、骨粗鬆症の発症リスクが高まります。こうした疾患や治療薬が原因となる骨粗鬆症を「続発性骨粗鬆症」と言います。
女性ホルモンと骨粗鬆症の関係
女性ホルモンの一種であるエストロゲンにより女性の身体が守られており、骨密度・骨質を維持する働きもあります。更年期に入るとエストロゲンの分泌が不安定になるため、閉経後はエストロゲンの減少に伴って骨密度・骨質が低下することで骨粗鬆症の発症・悪化に繋がります。日本人の女性は、60代では約5割、70歳以上になると3分の2の方が骨粗鬆症を発症していると言われています。
なお、骨粗鬆症は、予防・治療により発症・悪化を防止することが可能です。
閉経の平均年齢である50歳を迎えた方は、症状の有無に関わらず骨密度検査等を受け、医師の指示に従って食事・運動を見直しましょう。
骨粗鬆症の診断
 問診で症状の有無、既往歴、現在服用中のお薬などについてお伺いします。その後、骨密度検査、レントゲン検査、血液検査、尿検査などの検査を実施し、これらの結果から総合的に判断します。
問診で症状の有無、既往歴、現在服用中のお薬などについてお伺いします。その後、骨密度検査、レントゲン検査、血液検査、尿検査などの検査を実施し、これらの結果から総合的に判断します。
骨折をきっかけに受診された患者様には、骨粗鬆症による脆弱性骨折ではないか調べることが必要です。本来、骨折は強い外力の衝撃によって発生しますが、脆弱性骨折では本来であればなんともないような些細な衝撃で骨折してしまいます。脆弱性骨折の場合は骨密度を測定して骨粗鬆症の有無を確認し、骨折治療と並行して骨粗鬆症の治療も進めます。
骨粗鬆症の予防・治療
骨粗鬆症の治療は、骨折の予防・生活の質の維持が目的で、骨強度(骨密度・骨質)を高めて骨を強くし、ぶれない体を作ることで転倒による骨折を防ぎます。加齢に伴う骨格・体つきの変化を予防し、日常生活動作を維持して、生活の質の低下を防ぐこと、つまり、骨・骨格の健康(Bone Health)の維持・増進です。
治療は、食事療法、運動療法、薬物療法に分けられます。各患者様の骨折リスクなどをもとに適切な治療法をご案内します。
骨のリモデリング
骨は、破骨細胞による骨吸収と骨芽細胞による骨形成を繰り返して骨強度(骨密度・骨質)を維持しており、この過程を骨のリモデリングといいます。
骨強度を高めるために、骨の主成分であるカルシウムとタンパク質だけでなく、骨の形成をサポートするビタミンDやビタミンKなども十分に摂取する必要があります。
食事療法
バランスの整った食事を意識しましょう。また、カルシウムやタンパク質、ビタミンD、ビタミンKも十分に摂取するようにしてください。なお、糖質や脂質、リン酸、酸性食品は過剰に摂取すると骨粗鬆症のリスクを高めるため、控えるようにしましょう。
必要な栄養素
カルシウム 700~800mg (食品のカルシウム)
乳製品、魚介類(しらす、さくらえび、干しえびなど)、大豆製品、昆布、小松菜、モロヘイヤなど
ビタミンD 400~800IU
サンマ、鮭、ブリ、しらす干し、干ししいたけ、卵など
ビタミンK 250~300μg
小松菜、ブロッコリー、ホウレンソウ、鶏肉、納豆など
タンパク質やイソフラボン
魚、肉、大豆製品(納豆、豆腐、豆乳など)
以下の食品・飲み物は過剰摂取に注意しましょう
肉類、ハム・ベーコン、インスタント食品、果物、洋菓子、人工甘味料、マーガリン、食塩、リン、カフェイン、アルコールなど
運動療法
骨に負荷をかける運動は骨密度を高め、骨の強度が高まります。運動不足や寝たきりの状態では骨密度が低下し、骨が脆くなりやすいです。また、運動によりぶれない体を作ることで、転倒による骨折を防ぐことが可能です。
運動は習慣的に続けられる軽いもので十分です。
当院では、患者様の状態に応じた適切な運動メニューをご提案しており、トレーニング指導を丁寧に行っています。お気軽にご相談ください。
薬物療法
骨粗鬆症の治療薬では、骨を壊す破骨細胞と骨を作る骨芽細胞のバランスを整えます。以下の3種類に大別されます。
- 古くなった骨を壊す働き(骨吸収)を抑制するお薬
- 新たな骨を作る働き(骨形成)を促すお薬
- 骨の成分を補う、もしくは破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスを整えるお薬
治療薬には様々な種類があり、患者様の年齢、生活習慣、骨折リスク、骨折部位などに応じて適切な薬剤を処方しています。
骨粗鬆症の治療薬は、医師の指示に従って服用を続けることで、骨密度を増加させて骨折リスクを低減する効果が期待できます。薬物療法の主な対象者は、骨を維持するのに大切な栄養が不足している方、運動不足の方、骨量の低下を招く疾患を患っている方、脆弱性骨折が起きた方などです。
いつのまにか骨折と骨粗鬆症
骨粗鬆症では骨強度(骨密度・骨質)が低下して骨が脆くなり、重症化した場合はくしゃみなど些細な衝撃でも骨折することがあります。
「いつの間にか骨折」とは背骨の椎体が潰れるように骨折した状態で、痛みに気づかないことも多いことから呼ばれるようになりました。正式には「骨脆弱性椎体骨折」と言います。
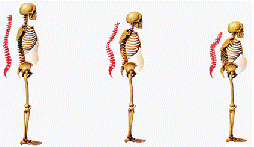
骨粗鬆症による脊椎の圧迫骨折
背中が曲がって身長が低下し、重心が前方へ移動するため、転倒しやすくなります。
些細な衝撃でも骨折しやすくなります
骨粗鬆症による骨強度(骨密度・骨質)の低下が進むと、骨が脆くなっていき、ちょっとした衝撃でも骨折しやすくなります。例えば、転倒して地面に手をつく、軽くしりもちをつくなどです。また、自重により気づかないうちに背骨を圧迫骨折し、背中が丸くなる、身長が縮む、腰が重いなどの症状をきっかけに、骨折していたことが発覚することも少なくありません。
骨粗鬆症が原因の骨折は痛みをほとんど伴わないこともよくあり、上述した「いつの間にか骨折」が認められることも多いです。
周囲の骨が連鎖的に骨折する可能性も
「いつの間にか骨折」では骨折部位のみならず、周囲の骨も同様に脆くなっています。体重を支えるために、骨折部位の周囲の骨に必要以上に負荷がかかってしまい、連鎖的に骨折する可能性があります。些細な動作でも骨折するようであれば介護なしでは日常生活を送るのが困難になり、さらに悪化すると寝たきりの状態になる恐れもあります。