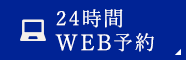ブロック注射
 ブロック注射は、痛みのある部位の支配神経近傍に麻酔薬を注射することで、痛みを軽減する治療法です。外来で行われ、保険が適用されます。
ブロック注射は、痛みのある部位の支配神経近傍に麻酔薬を注射することで、痛みを軽減する治療法です。外来で行われ、保険が適用されます。
全身の様々な部位に対して行うことができ、首、肩、手足、腰、膝などが対象となります。
麻酔薬を注射すると聞くと鎮痛効果は一時的なものとイメージされますが、ブロック注射の場合、痛み自体を緩和すること以上に、痛みの原因となる神経の興奮を抑えることができます。痛みが起きていると神経が興奮して筋肉が緊張し、血管が収縮することで血行不良が起きることで発痛物質が生成されます。発痛物質の放出により神経が刺激されるという悪循環に陥り、痛みが続いてしまいます。
ブロック注射は神経の興奮を抑えることで、筋肉の緊張が和らぎ、血流が改善されます。これにより、患部に酸素や栄養素が正常に供給され、老廃物も体外に排出されることで、痛みが治まります。血流が改善されることで、麻酔が切れても患部の状態が良くなるため痛みの緩和につながり、良循環へまわすきっかけとなります。
適応疾患
- 坐骨神経痛
- 椎間板ヘルニア
- 脊柱管狭窄症
- 神経根症
- 関節リウマチ
- 慢性的な腰痛 など
関節注射
変形性関節症や関節炎で痛みの原因が関節包内にある場合に効果が期待できるのが、関節注射です。関節包は、関節全体を包み込む袋状の組織で、関節の安定性を保つとともに、滑らかな動きを支える重要な役割を担っています。この関節包内の関節腔へ直接ヒアルロン酸、ステロイド、局所麻酔などを注射することで、関節の炎症や痛みを抑えます。痛みが強い場合は短時間で症状の緩和が期待できます。また、局所的に作用するため副作用は少ないですが、ステロイド注射の場合は稀に全身性の副作用が現れることがあるため、医師と相談の上で治療を進めます。
- ヒアルロン酸:関節の滑りを良くし、衝撃を吸収します。
- ステロイド:強力な抗炎症作用で痛み、腫れを軽減します。
- 局所麻酔:痛みを一時的に遮断します。
適応疾患
- 変形性関節症
- 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
- 関節リウマチ
- 肩関節炎・足関節炎 など
トリガー注射
筋肉の中に存在する「トリガーポイント」と呼ばれる、硬くなった痛みの原因となるツボのような部分に局所麻酔薬や生理食塩水を直接注射します。首、肩、背中、腰、四肢など全身の筋膜や腱膜の痛みに効果が期待できます。
痛みの原因となる筋肉に直接注射するため、短時間で痛みが改善することが多いですが、効果が一時的となるため、再発しやすく、原因を排除するための治療やリハビリテーションも同時に実施することが必要です。
適応疾患
- 肩こり
- 慢性的な腰痛
- 首の痛み など
ブロック注射・関節注射・トリガー注射の比較
| 項目 | ブロック注射 | 関節注射 | トリガー注射 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 神経近傍 | 関節 | 筋肉(トリガーポイント) |
| 主な作用 | 痛みの信号遮断 | 炎症抑制・潤滑作用 | 筋肉の緊張緩和 |
| 即効性 | 高い | 高い | 高い |
| 持続期間 | 数日〜数週間 | 数日〜数ヶ月 | 数日〜数週間 |
| リスク | 感染、注射部位の内出血 | 同左 | 同左 |
ブロック注射・関節注射・トリガー注射の流れ
1初診
 まずは問診表に症状などを記入して頂きます。保険証とお薬手帳(日頃から飲んでいるお薬がある方)をお持ちください。また、紹介状(診療情報提供書)や他院の撮影画像をお持ちの方は、それらもご持参ください。
まずは問診表に症状などを記入して頂きます。保険証とお薬手帳(日頃から飲んでいるお薬がある方)をお持ちください。また、紹介状(診療情報提供書)や他院の撮影画像をお持ちの方は、それらもご持参ください。
2保険証を必ずお持ちになってお越しください
いずれの注射療法も健康保険が適用されるため、保険証を忘れずにお持ちください。
保険証を提出頂いた後、問診表を記入して頂きます。
3検査と診療
 問診表の内容に沿って医師が症状などをお聞きした後、レントゲン検査や血液検査などの必要な検査を実施します。
問診表の内容に沿って医師が症状などをお聞きした後、レントゲン検査や血液検査などの必要な検査を実施します。
問診・検査結果から注射の適応が判断されれば、治療内容について丁寧にご説明します。治療は患者様に内容を十分にご理解頂き、納得頂けた場合のみ行います。
よくある質問
注射は痛いですか?
痛みは注射の種類によって異なり、強い痛みを感じる場合もあります。当院では細い針を採用しており、できるだけ痛みを抑えるように工夫しています。経験豊富な医師が注射を実施しておりますので、安心してご相談ください。
どのくらいの頻度で注射できますか?
ブロック注射・トリガー注射は、症状により、週1回可能です。関節注射の、ヒアルロン酸は週1回を3〜5回、その後は月1回程度が目安。ステロイドは多くても年間3〜4回が推奨されます。
注射後に痛みが増すことはありますか?
稀に「フレア現象(反応性関節炎)」で一時的に痛みが増すことがありますが、1〜2日で治まることがほとんどです。
注射で関節が治るのですか?
関節の骨格変形は変わりません。痛みのコントロールが目的です。痛みが和らいだ後は、リハビリや筋力トレーニングが必要です。