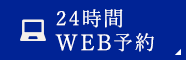四十肩・五十肩とは
 「四十肩・五十肩」で知られる40代・50代の方が悩まされる肩の症状は、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれています。日本においては、全人口の2~5%がこの疾患を発症しており、特に40~60代の女性に好発しています。また、糖尿病を患っている方は糖尿病でない方に比べ、肩関節周囲炎を発症しやすく、糖尿病患者の10~20%が合併していると考えられています。
「四十肩・五十肩」で知られる40代・50代の方が悩まされる肩の症状は、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれています。日本においては、全人口の2~5%がこの疾患を発症しており、特に40~60代の女性に好発しています。また、糖尿病を患っている方は糖尿病でない方に比べ、肩関節周囲炎を発症しやすく、糖尿病患者の10~20%が合併していると考えられています。
症状は肩から腕にかけての急激な痛みです。明確な原因は分かっていませんが、医療機関で肩関節周囲の可動域や硬直具合、関節の動き方、全身の状態を調べると、肩以外の部分に起きた異常から肩に負荷がかかっているケースが多いです。そのため、治療は肩だけでなく、その周囲の部位も含めて行うため、長期にわたることが一般的です。当院では、まずは疼痛軽減のための薬物療法や運動療法などを行います。関節内注射を行う事もあります。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の症状
- 肩関節が痛い
- 肩を動かした際に痛みを感じる
- 肩の可動域が狭まり、動かしにくい
- 就寝中に肩に痛みを感じて目が覚めてしまう
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の病期
肩関節周囲炎は、急性期、慢性期、回復期の3段階に分類されます。段階に応じた適切な治療を行うことで改善が期待できますが、症状が治まるまでには6ヶ月~1年ほどかかります。
急性期
初期は肩の不快感や痛みが主な症状で、2週間~1ヶ月程度持続します。夜間になると痛みが強く出る傾向があるため、十分な睡眠がとれないこともあります。また、肩を冷やすと痛みが強くなるので、保温するなど冷やさないように気を付けましょう。痛みが強い場合は肩を動かさないように安静にする必要がありますが、ずっと動かさないでいると柔軟性が低下しリハビリ期間が長くなる可能性があるため、無理のない範囲で適度に動かしましょう。
慢性期
慢性期では、肩の不快感や痛みは解消しますが、肩関節が固くなり拘縮するため、肩を上にあげる動作(外転)や後ろに動かす動作(伸展・内旋)が困難になります。
このように肩が凍りついたように動かなくなる様子から、慢性期は別名「凍結期(frozen shoulder)」とも呼ばれています。
慢性期では肩のあらゆる動きに制限がかかるため、日常生活にも支障が出ることが特徴です。理学療法が主な治療法となりますが、必要に応じて注射などを実施します。
回復期
回復期では、可動域も徐々に元に戻り、痛みなどの症状も解消することが多いです。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の検査・診断
肩の痛みの原因は肩関節周囲炎に限らず、肩関節炎や上腕二頭筋腱炎、肩峰下滑液包炎、肩峰下インピンジメント症候群、石灰性腱炎、変形性関節症、回旋腱板断裂なども挙げられます。このように様々な原因疾患があるため、適切な治療を行うためにも正確な診断が求められます。
肩関節の動きは筋肉や靭帯が特に重要な役割をもっており、レントゲン検査のみでは異常を確認することが困難なこともしばしばあります。症状により、超音波検査を行い、肩関節を構成するこれらの組織の診断が可能です。回旋腱板や肩関節腔、二頭筋腱周囲、肩峰下滑液包などの状態を詳細に調べ、適切な治療につなげています。MRIなどの検査が必要な場合、提携している高度医療機関をご案内し、スムーズに検査を行えるように体制を整えています。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の治療
薬物療法
急性期は強い炎症が起きるため、消炎鎮痛剤(内服薬・外用薬)を使用した薬物療法を実施します。なお、肩関節周囲炎では神経痛治療薬などの方が効果を発揮することもあり、症状に応じた適切な薬剤を選択します。痛みが強い場合、関節内注射を行う事もあります。
注射・サイレントマニプュレーション
注射治療は、肩関節や肩峰下滑液包、二頭筋腱周囲に対し、ヒアルロン酸、局所麻酔薬、ステロイド鎮痛剤などを注射で投与します。
一方、サイレントマニピュレーションは、患部に麻酔をかけて痛みを抑えた状態で医師が手で直接可動域を拡げる治療で、慢性期の肩の拘縮を改善するために行われます。
リハビリテーション
 姿勢や動作の改善指導、肩関節の可動域訓練、再発予防のためのリハビリテーションを行います。肩関節周囲炎が起きている場合、肩関節に必要以上の負荷がかかる動作・姿勢となっていることが多いです。そのため、再発を防ぐためにも動作や姿勢の改善、可動域訓練が欠かせません。
姿勢や動作の改善指導、肩関節の可動域訓練、再発予防のためのリハビリテーションを行います。肩関節周囲炎が起きている場合、肩関節に必要以上の負荷がかかる動作・姿勢となっていることが多いです。そのため、再発を防ぐためにも動作や姿勢の改善、可動域訓練が欠かせません。